日本高野連が加盟各学校に向けたタイブレークに関するアンケート結果を公表しました。それによると、タイブレークに賛成しているのはほぼ半数の49.7%。やる方としてはやはり、選手への負担を考えるとタイブレークは必要かもしれないという考え方は自然かもしれません。
いろいろと細かいところが報じられているのを見てみると、半数近くが賛成とはいえ「世界的な流れになってきているならあってもいいだろう」など条件付きの賛成という意見が多いということで、必ずしも前向きな賛成が大勢を占めているわけではないようです。まぁ、回数制限、投球数制限を認めてもいいという意見は1割前後というのもうなずけます。「やれと言われたらやるけどさ」というのが本音かもしれません。
「タイブレークをやるとしたら何回からがいいか」という質問に対しては13回からがいいという意見が最も多かったとか。12回までならよくあることだからということでしょう。これ以上続くと戦力が落ち込むかもしれないから労力をかけないようにしようというふうに考えているのかと思います。
さっきにも言いましたが、今回のアンケートはやる方の率直な気持ちが浮き彫りになったかと思います。東京では甲子園にかかわりがない大会で試験的にタイブレークを導入するそうです。これを一つの材料としていい結論を導いてほしいものです。
それでは、また次回です。
夏の甲子園が終わった後も、もう一つの高校野球でものすごいゲームがあったとか。日本高野連が主催するもう一つの高校野球とは「全国高校軟式野球選手権」。軟式野球の場合、小学生から社会人までを統括する組織として全日本軟式野球連盟がありますが、高校の軟式野球だけは日本高野連が全日本軟式野球連盟から独立して運営しています。この組織関係がもしかしたら、ドラマを起こしたのかもしれません。
8月31日までの4日間かかって50イニングも戦い続けたという準決勝の中京(岐阜=愛知・中京大中京とは無関係=)-崇徳(広島)。49回まで0-0が続くというゲームは50回表に中京が3点とって勝負を決めました。なんでこんなことになったかといえば、高野連が独自に作ったレギュレーションにあります。全日本軟式野球連盟の大会ならば、ある程度のイニングまたは時間が過ぎたらタイブレークにして勝負を早く決めるようにしますが、こちらの場合は15回まではとりあえずやり続け、勝負付かなければ後日持越し(サスペンデッド)になります。タイブレークならばランナーを置いてスタートさせますが、サスペンデッドは0アウトランナーなしからスタートになります。タイブレークなら単打(シングルヒット)1本で1点は取れますが、サスペンデッドではヒットが1本出ても後が続かなければ点が入らず延々と試合が続くこともあります。
なぜ、高野連はサスペンデッドを選ぶのか? これは硬式野球の引き分け再試合との比較があるからと言われています。軟式は肩肘の負担が軽いのであまり長く投球間隔を置く必要がないのでサスペンデッドを選んだという説明が各メディアに掲載されています。高校野球ならではの事情があるようです。といっても、バットの芯にボールをしっかりと当てられなければ飛びにくいし点も取りにくいと言われる軟式野球の特性をとらえたタイブレークを軟式野球限定で扱わないのかという疑問も私の中ではあります。もしかしたら、甲子園大会でのタイブレーク制導入に対しての議論に今回の延長50回が何かしらの影響を及ぼすかもしれませんね。
次回はアギーレジャパンの話でも(予定は未定です。変わる可能性もあります)。
第96回全国高校野球選手権は25日に決勝が行われ、大阪桐蔭が平成最多を更新する2年ぶり4度目の優勝を果たしました。振り返れば、大阪桐蔭は正攻法の典型と言ってもいいような戦いぶりで優勝までたどり着いたような気がします。そんな中でも高校野球の常識を挑戦する個性派が今年もたくさん現れました。
特に注目を集めたのは東海大四高(南北海道)の西嶋投手。60kmを切るといわれる超スローカーブを武器にして1勝しました。4m以上浮き上がりちゃんとミットに収まるわけですから、スタンドは拍手喝采となります。そのあとに普通にストレート(130km台後半)を投げれば落差は70km以上になるわけですから、変化球を覚えなくてもチェンジアップの代用品を得られるというわけです。コントロールの良さも加われば鬼に金棒。味方からも「投げ過ぎないほうがいい」と注意されたことがあるらしいですが、本人はそれでも投げ続けると言い切っているとか。ツイッターでは、最近はWOWOWのスポーツ実況を多く担当する岩佐徹さんが「誰が何と言おうとあれは投球術じゃないといい続けてやる」というようなことをつぶやくと、なんとレンジャースのダルビッシュ投手が「スローカーブは難しいもので、自分のものにしているのは素晴らしい。(批判される筋合いはない、ということ?)」という具合に応酬という「場外乱闘」もありましたね。
攻撃面で注目を集めたのは高崎健康福祉大高崎(群馬)の機動力。「機動破壊」というキャッチフレーズを掲げて1日に2時間以上走塁練習をしてきたということもあってか、盗塁の戦後最多記録、戦後タイ記録を立て続けに打ち立てました。走塁にはスランプはないといわれていますが、バント以上に盗塁で相手の守りを崩しにかかるような発想は今までなかったような気がします。
しかし、大量リードをとっているところでの盗塁はメジャーリーグでは伝統的な不文律に背くことになってしまうので、メジャー以外でも「花相撲」でなければ遠慮すべきという考え方も浸透しています。そのためか、この「機動破壊」の考え方がネット上で批判されたとの記事がYahoo!スポーツに掲載されたこともあります。その批判に乗ったわけではないでしょうが、大阪桐蔭の西谷監督は準々決勝で対戦する前に「盗塁だけじゃ3塁までしか行けないから」と見方次第では挑発と取れるような発言をしていました。結局は強打で見事「機動破壊」の高崎を打ち破る結果となりましたが。でも、新たな発想の戦術としてこれからの高校野球に何かしらの影響をもたらしてくれるはずです。
大阪桐蔭のようにしっかり守ってしっかり打つという常識通り、セオリー通りのやり方を貫いて優勝できたことは確かに素晴らしいことです。しかし、何かしらの新しい発想のきっかけをもたらしてくれるようなプレーがいつでも生まれてくるのが高校野球の魅力だと思うんです。これからもまた楽しみます。
それでは、また次回です。
今回から木曜または金曜の更新で続けていこうと思います。引き続きおつきあいください。
96回目の夏の甲子園が9日に開幕しますが、今回は先月29日まで行われた都市対抗野球のことを。
85回の記念大会となった都市対抗は岐阜県大垣市の西濃運輸が高校野球ばりのエース中心の投手起用が見事にハマリ初優勝を果たしました。そして、今回から地上波での本格的な放送が復活しました。ここ数年はNHKのBSで準決勝と決勝を放送している以外はCSでの放送のみという状況で、高校野球のように気軽にテレビで楽しめるような感じにはない印象がありました。もっと言ってしまえば、社会人野球ってマニアックな存在なのかなとも疑ってしまう印象もありました。
しかし、今年、関東ローカル(tvk、チバテレ、テレ玉、群馬テレビ、とちぎテレビの独立系5局)ではありますが地上波でデイリーダイジェストが放送されました。要は、都市対抗版「熱闘甲子園」が始まったんです。といっても、負けたチームの選手たちがベンチ裏の通路で「先輩、勝てなくてすみません」「お前は悪くない! 今度はお前たちが1・2年を甲子園に連れていく番だぞ!」と泣き叫ぶシーンを「お約束」のように流すことはなく、ゲームダイジェストを淡々と流し専門解説を要所に挟み込むいたってシンプルな構成。でも、その中でスタンドでの応援の様子やマスコットガールのメッセージを織り込んで都市対抗らしさを演出している感じもありました。
こういう番組で都市対抗ってこういうものなんだって知るきっかけが間違いなくできると思います。そして、時間があれば東京ドームに行ってみようかなっていう動機づけになると思うんです。社会人野球、都市対抗野球が高校野球と同じくらいに親しまれるきっかけになることを期待します。
それでは、また次回です。
プロ野球もメジャーリーグも後半戦に突入し、都市対抗野球の全国大会がスタート、夏の甲子園の各地域代表もぼちぼち決まり始め、いつもより長いサッカーの季節が終わりいよいよ野球の季節が本格的に動き出しました。そんなさなか、世論を二分しかねない構想が浮かび上がりました。
来年のセンバツ高校野球を目安に、甲子園大会でもタイブレーク制度を導入することを日本高野連が検討に入ったというんです。このことが報じられると、スポーツ各紙では賛否両論が交わされるようになりました。賛成意見の根拠といえば、「選手の体力的な考慮をすれば当然のこと」というのが基本線にあるようです。一方、反対意見の根拠は「高校野球らしさが損なわれてしまう」「選手の努力を否定するようなもので到底受け入れられない」といった感じ。
考えてみると、タイブレークって、U-18世界選手権でもう使われているし、国内でも国体ですでに採用されているというんです。いわば、木のバットやDH制、ボールカウントと同じようにタイブレークもワールドスタンダードのひとつの形といえるでしょう。それにいち早く触れるためにも必要かもしれません。ただ、高校野球は「ハイスクールベースボール」でなくて日本独特の「KOKO YAKYU」なんだという考え方も一方にあります。たとえば、15回まで死力を尽くして戦い、決着ついても、決着つかず引き分け再試合になったとしてもお互いが肩を抱き合い健闘をたたえてスタンドの誰もが拍手する、そういうシーンに日本らしさを見出す人もいるようです。
そんな中、私はなるほどと思えるような意見を見つけました。報道された翌日のスポーツ報知に、国内野球やメジャーリーグを取材して40年以上という蛭間記者がタイブレーク制度を導入する代わりにこれまで高校野球で導入されなかったサスペンデッドゲームを採用したほうがいいと提案しているんです。これなら、引き分け再試合になったら15回+9回=24回やらなければいけない現行制度から考えると選手の体力消耗がある程度抑えられるでしょうし、タイブレークでこれまでの流れをリセットすることもないわけです。もっと言ってしまえば、選手たちの努力を否定することには通じないといえそうです。
ワールドスタンダードか伝統かという二者択一でまとめられる問題ではないでしょうが、誰もが納得できる落としどころを見出せることを祈ります。
それでは、また次回です。
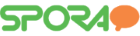
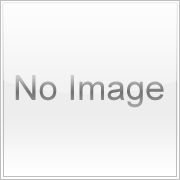
 最新投稿RSS
最新投稿RSS